日本はAIを活用して公共交通に革命をもたらし、交通空白地帯と戦う;
最先端技術は、高齢者を医療につなげ、観光客の旅行を合理化し、全国的なアクセシビリティを向上させることを目指している。
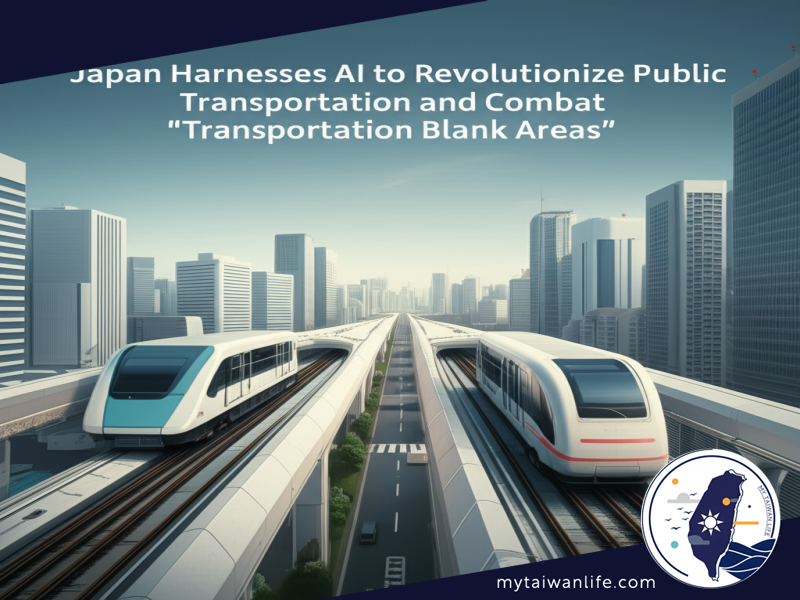
東京発 – 日本の国土交通省は、公共交通機関へのアクセスが限られている「交通空白地帯」の問題に対処するため、デジタル技術と人工知能(AI)を活用するという画期的な取り組みに着手します。
この野心的な計画は、すべての国民、特に高齢者や観光客のニーズに焦点を当て、利便性を向上させることを目指しています。国土交通省は、AIを活用して、通院の高齢者向けに予約制バスの運行を最適化し、人気の観光地を訪れる観光客向けにタクシーの利用を確保する予定です。この革新的なシステムを2030年頃までに全国で完全に運用開始することを目指しています。
具体的な計画は先月発表され、今会計年度には約20件の実験が予定されています。そのうちの重要な実験の一つが徳島県で行われ、病院から自宅までの患者を輸送する予約制バスの効率化に焦点を当てます。富士通株式会社は、患者が医療を受ける時間や会計手続きにかかる時間を予測するシステムの開発を主導します。
徳島県立中央病院の予約システムは、地元のタクシー協会のバス配車システムと統合されます。この統合により、患者の出発予定時刻直前にバスを配車し、待ち時間を最小限に抑えることが可能になります。
北海道では、旭川空港が、空港から観光地へのシームレスな移動を促進するシステムを開発しています。航空会社は、到着する乗客数やフライトの遅延に関する重要な情報を地元のバスおよびタクシー会社と共有し、これらの会社が到着時刻と出発時刻を調整できるようにします。東京の乗り換え案内検索ソフト会社であるジョルダン株式会社が、このシステムを開発します。目的は、到着する乗客のニーズに応えるために、十分な数のタクシーを空港で利用できるようにすることです。
日本は近年、乗客数の減少の影響を受け、鉄道とバスの運行が減少しています。これは、高齢者が交通手段の制約のために医療を受けることが困難になる可能性のある過疎地で特に顕著です。さらに、一部の観光地では、国内外からの観光客の増加により、公共交通機関に対する需要の高まりに対応するのに苦労しています。
ライドシェアサービスは潜在的な解決策として拡大していますが、ドライバー不足は依然として課題です。昨年、国土交通省は交通機関の不足に対処し、新たな解決策を模索するために官民連携を設立しました。国土交通省は、AIやその他の民間セクターの技術を活用して、効率性を向上させ、人手不足に対処する意向です。
Other Versions
Japan Harnesses AI to Revolutionize Public Transportation and Combat "Transportation Blank Areas"
Japón aprovecha la IA para revolucionar el transporte público y combatir las "zonas vacías de transporte"
Le Japon exploite l'IA pour révolutionner les transports publics et lutter contre les "zones vierges de transport" ;
Jepang Memanfaatkan AI untuk Merevolusi Transportasi Publik dan Memerangi "Area Kosong Transportasi";
Il Giappone sfrutta l'intelligenza artificiale per rivoluzionare il trasporto pubblico e combattere le "aree vuote dei trasporti"
일본, AI를 활용하여 대중교통을 혁신하고 '교통 사각지대'를 해소합니다;
Ginagamit ng Japan ang AI upang Baguhin ang Pampublikong Transportasyon at Labanan ang "Mga Walang Saklaw na Lugar sa Transportasyon"
Япония использует искусственный интеллект для революции в общественном транспорте и борьбы с "транспортными пустотами"
ญี่ปุ่นใช้ AI ปฏิวัติระบบขนส่งสาธารณะและแก้ไขปัญหา "พื้นที่ขนส่งว่างเปล่า"
Nhật Bản Ứng Dụng AI để Cách Mạng Hóa Giao Thông Công Cộng và Chống Lại "Vùng Trắng Giao Thông"

